「意識」を語る
読み易さ:難★★★★★☆☆☆☆☆易面白さ:眠★★★★★★★★☆☆興
専門性:一般★★★★★★★☆☆☆専門
有用性:趣味★★★★☆☆☆☆☆☆実用
総合評価:ビミョー★★★★★★☆☆☆☆オススメ
「意識」というものは現在、神経科学や認知科学における一大テーマとなり、活発な研究と議論が行なわれている。
といっても、議論が起こっているということは、「まだ分からないことだらけ」ということでもある。
そのことをまさにありのままに描き出しているのが、この『「意識」を語る』
この本は著者のスーザン・ブラックモア氏が、「意識」をテーマに研究を行なう第一線の研究者たちにしたインタビューをまとめたものだ。
さて、この本のなにがすごいって、そのインタビューを受けているメンツがすごい。
「中国語の部屋」のジョン・サール
言わずと知れたクリストフ・コッホ
『脳のなかの幽霊』でおなじみのヴィラヤヌル・ラマチャンドラン
「微小管」のロジャー・ペンローズ
そして、2005年に惜しくも亡くなられてしまった、われらがフランシス・クリック先生
見てるだけでよだれ…は垂れないけど、生協ででこれをみつけたときには本当に驚いた。
こんなメンツありか?って。
で、肝心のインタビューの内容はというと、これがひとによって(ほんとうに)さまざま。
ただし、著者が序文で述べているように
・哲学者のゾンビを信じるか?
・自由意思はあると思うか?
インタビューアによるこのような一貫した問題提起が、研究者に「意識」というとりとめもないテーマを語らせながらも、本全体としての一貫性をもたせている。
(ちなみに「哲学者のゾンビ」「自由意思」は、ともに「意識」と密接に関係する概念ですね。)
一方で著者は、多くの研究者に対して
・「意識」の研究をしていて、なにか自分の意識が変わったか?
このような質問は、血まなこで自分の理論を展開している姿からは思いもよらなかった、研究者の人間くさい一面を描き出している。
ひとによっては、それまでの理路整然としたロジカルトークは何だったのかと思えるような、宗教観や生命観をみせたり。
著者のスー・ブレイクモアはフリーランスのライターだが、長年、意識やミームといった「人間存在」に関する研究もしているひと。
『ミーム・マシンとしての私』は有名なので、あの本の著者だといえば分かりやすいかな。
そして彼女は、その学歴(超心理学での博士号),活動(ドラッグ合法化の主張),興味(仏教・禅への傾倒と実践)など、まあ「普通の」ひとではない。
これがどうも、本書のような本を生み出すことができた、大きなポイントでもあるようだ。
すなわち意識の問題は、研究者によって宇宙のスケールから微小管まで、いうことはホントにさまざま。
そのすべての議論に対して、物怖じせず、一笑に付すわけでもなく、真面目にはなしを聞き、真面目にツッコむ彼女は、まさに奇人といっていいと思う。
読んでいると、どうにも
まあときどきトンチンカンな受け答えをしたりもしているが。
内容的な面でいうと、インタビューだけあって、さすがにいちいち専門用語の解説がされたりはしない。
会話の記録である以上、インタビューする側とされる側が共通に認識している語彙については、なんの説明もなく使われている。
なので、この分野のはなしをまったく知らない人が読むのは、それなりにつらいかもしれない。
また、前知識なしのまっさらでは、トークの面白さも十分には味わえないと思うし。
(もちろんその研究者の理論の根幹に当たる概念には、必然的に詳しい記述がつくことになるが。)
ただ本の最後に簡単な用語集が付いているので、ムリというわけではない。
そもそもこの本を読んで、
だからビビる必要はないだろう。
ある意味、だれも分かってないことに関する縦横無尽の議論だから、気楽に読めばいいと思う。
お堅い本で哲学用語の勉強をするよりは、よっぽど意識に関するいろいろな概念や用語を学べるだろうし。
で、最後にいちおう、批判的なことも書いておく。
本書は訳本だが、訳はこなれたかんじで読みやすいし、大きく間違っているカンジの部分も見られなかった。
それはいい。
だけど、なんとなく翻訳者が気に入らない。
たとえば書籍の帯にあるこのコメント(NTT出版のサイトにも書いてある。)
この分野は今現在、肥大に肥大を重ねていて、一線の研究者でさえ誰一人としてすべてを把握してなんていないだろうに。
しかも訳者あとがきでは、本書でインタビューされている研究者の一部を、それこそ一笑に付したあとで、自分自身は
いや、それは観察者のバイアスだよ。
いくらなんでもそれはないわ。
それから、これは付加的な問題かもしれないけど、訳文に勝手にキャラをのせすぎです。
「~しとらんよ」とか「~ですのよ」とか。
まあインタビューだから、会話らしい感じにするための工夫なのだと思うけど。
読みにくいというわけではないが、ときどきちょっとやり過ぎなキャラ付けに感じた部分があった。
まあいちおう繰り返すと、べつに訳は悪いわけでなく、むしろ訳本のなかではとても読みやすくて良いと思う。
「生きた哲学用語(笑)」を身につける意味でも、興味のある人は読んでみて損はないでしょう。
ただしこの本での議論が、今後どのような方向に展開していくかも分からないので、一般的なおすすめ度は星6つにしておきます。
同業のかたに対しては、星9つでおススメしますが。
読んでみてください。
(2009.04.08)





 @kanri_ninjin
@kanri_ninjin
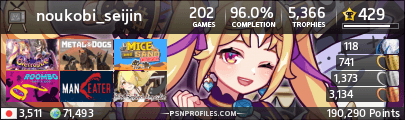


 イクナイ! 581
イクナイ! 581










